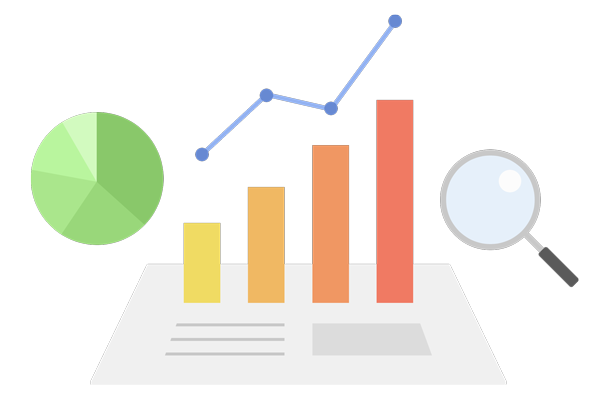ニュース
座間市議団ニュース 第300号 2025年4月
旧ごみ焼却炉の解体工事でアスベストが追加検出
3/28(金)午前9時から、ごみ処理を所管する高座清掃施設組合議会でした。同議会は海老名市、座間市、綾瀬市から各5人の議員で構成されています。
まず全員協議会で、旧ごみ焼却炉の解体工事の進捗状況が報告されました。解体工事で新たに発見されたアスベスト含有モルタルの量が9645㎡であり、解体工事の進捗が1年以上遅れるとのことでした。解体工事の遅れは地域交流温浴センターと剪定枝リサイクルセンターの遅れに影響します。「着工前のアスベスト調査ではなぜ見落としたのか?」「解体工事の作業が遅れた場合の違約金などの対応はあるのか?」など質疑しました。当局から「2006年のアスベスト法改正ではモルタルの扱いが曖昧で、2020年に規定されました。解体工事着手前の2022年に環境技術研究所とダイワがアスベストの事前調査をして、建屋のモルタルのサンプリング調査を実施しましたがアスベストが含まれなかったので全体的に建屋のモルタルにはアスベストが含まれないと判断しました。違約金の条項は業者側に問題がある場合であり、今回はアスベスト事前調査で見落としたことによる工事遅延なので、当てはまりません」との答弁でした。
続いて本会議では、職員の条例改正(118人から必要人員47人に、海老名市職員と同様の処遇)と当初予算が主な内容でした。当初予算54億4155万7千円で、事業系一般廃棄物処理手数料が1266万円増額の理由と基金積立金8550万円との関係を質疑しました。当局から「事業系廃棄物の予測量を聞き取りして対前年度422トン増加するので手数料を増額しました。手数料の値上げは2024年度から、10kgあたり250円が300円になった50円増額の分を基金に積み立てます」との答弁でした。今後もごみ処理の問題について取り上げます。【守谷浩一 記】
市政報告会のお知らせ
2025年5月6日(火・休)午後2時より、サニープレイス座間3階 研修室(座間市緑ケ丘1-2-1)で、党市議団主催の市政報告会を行います。
3月議会の報告とともに、地域のご要望などを承ります。
・小中学校体育館へのエアコン設置にむけては?
・高齢者世帯への火災予防機器の給付や購入補助は?
・有機フッ素化合物汚染への対応は?
言いたいこと聞きたいこと・・・双方向で語り合いましょう。
インフルエンザや新型コロナが流行しています。マスク使用は個人の判断でお願いします。諸般の事情によっては予定が変更になる場合もあります。
こども誰でも通園制度~その問題点
2025年座間市議会第一回定例会において、「こども誰でも通園制度」について一般質問を行いました。この制度は、2024年6月5日に、子ども・子育て支援法等の一部を改正して成立されています。 「こどもまんなか」を掲げる、こども家庭庁は「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため」として、保育施設に通っていない生後6か月から3歳未満の未就園児を対象に、月10時間ほどを上限に、保育所や認定こども園などで保育サービスを利用できるようにするというもので、本市でも2026年度からの実施が予定されています。
しかし、この新しい制度が本当にこどもの笑顔につながるのかどうか、
以下のことがらについて質問をしました。
①制度開始までの流れはどうなっているか②一時預かり事業との違いはなんなのか③先行自治体の状況は聞き取っているか④この事業は公立・民間に関わらず行うものなのか⑤現場の声は聞いたのか⑥保育士の負担増にはならないか⑦国がいっている、この制度の目的「親の育児負担の軽減や孤独感の解消」に対して本市はどのように関わっていくのか⑧アレルギー対応や事故防止などについての責任はどこにあるか⑨保育所では行われている「ならし保育」は行うのか⑩利用料は誰が決めるのか⑪利用は市内事業所のみか、市外でも可能な(自由利用)とするのか⑫パブリックコメントでの反応はどうであったか⑬6か月から3歳のこどもの成長過程において、この制度を利用したときに与える影響についての考察はしたか。 しかし、当局からの答弁は一貫して、「国からの基準がまだ示されてないので明言できない」というものでした。
自治体の責任でより良い保育を
児童福祉法第3条の2には、「国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。」と記されています。各自治体は保育の足りない子どもたちに保育の確保をしなければならないのです。
確かに新しい制度を利用するにあたって、保護者の就業の有無は足かせにはなりません。だからといって、ならし保育(本市では「慣れ保育」といいます)もなく、月10時間程度の保育ではこの制度を利用するこどもも、もともと保育園を利用するこどもにも、大きな負担になってしまいます。自治体に本来求められるのは、公設の保育園を増やして、こどもたちがのびのびと保育を受けられる環境を作ることです。しかし、ここでも大きな問題があります。国が民間の保育園へは助成はしますが、公設保育園への助成や補助をしなくなってきているのです。ここでも、国政と市政は切り離せない、大きな問題があるのです。
こどもの人権を尊重すること、一時的ではない保育を保障すること。とても大切なことを実現するためには、今を生きる大人の私たちが、しっかりとその土台を作っていかなければならないと考えます。一見すると、とても良い制度に思えてしまう「こども誰でも通園制度」ですが、本当の「保育」を行うために、来年の制度開始の前に再度質問を行い、座間市の保育をより良いものにしていくためにがんばります。【星野久美子 記】